静岡県教育委員会と常葉大学が共催する、「しずおか高校生探究フェスタ」が、1月26日に開催されました。会場となった常葉大学静岡水落キャンパスに、県内の高校から82チームが集い、コンテスト部門、交流部門、展示部門でそれぞれ発表を行いました。本校からは、2年生「総合的な探究の時間」から3チーム、学校設定科目「STEAM for SDGs」から2チーム、「海外研修」から1チームの、計6チームが交流部門に参加しました。開会式では、2年生の浅利優太さんが、全交流部門参加チームを代表して、意気込みを堂々とスピーチしました。
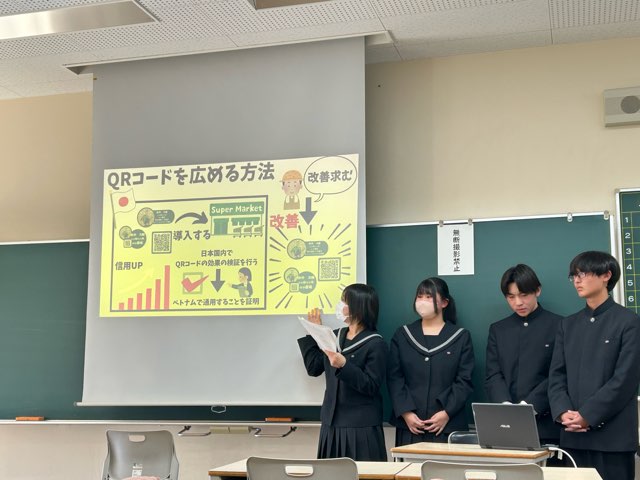
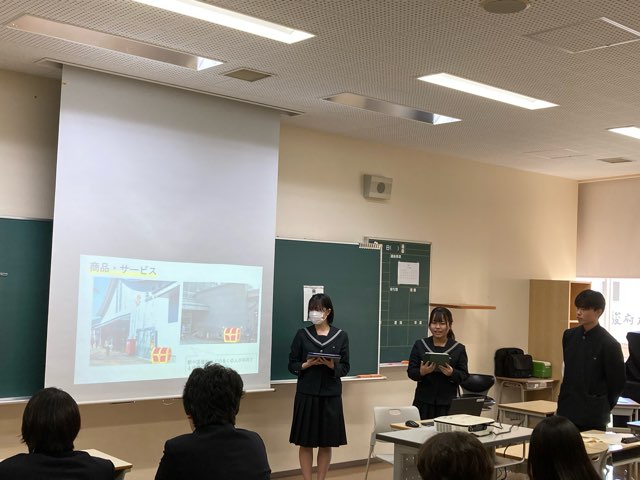
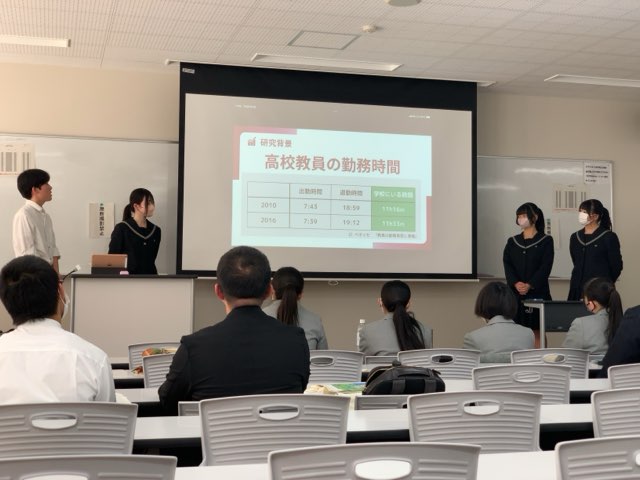

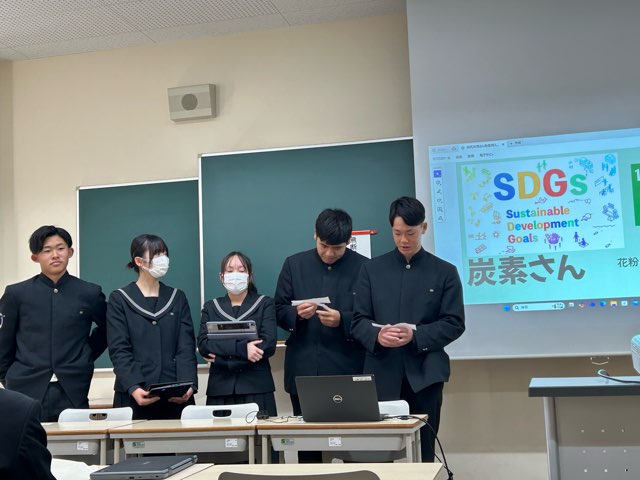



参加した生徒の感想
- 今回、私達はしずおか高校生探究フェスタの交流部門に参加させていただきました。5グループごとに探究学習の成果を発表し合いました。自分たちには無かった視点からの問題提起、多角的な解決策の具体的な考案の過程を聞いて、良い刺激になったと感じました。特に、「見た目ではわからない障がい者の避難所生活について」という発表に感銘を受けました。この発表における解決策は、紙のパンフレットで避難所にはどのような人がいるのか、特に精神障がい者の人々はどのような困難を抱えているのかを伝え、理解を深めるというものでした。発表者は、手元に残り、いつでも見返すことのできる解決策にしたかったため、あえて媒体を紙にしたと仰っていました。日本にいたら、誰もが災害について意識しますが、多くの人は防災を重要視すると思います。その中で、発表者は、災害"後"の避難所での問題を予測し、対策を考えていらっしゃいました。その着眼点、解決策の作成方法の工夫に感動しました。実際にパンフレットを拝見することもできました。グラフが載っていて説得力がある、わかりやすいものでした。手に取ることで、感じること、進言させていただきたいことなどが沢山浮かびました。 他の発表を聞いてその内容について深く考えることは、自分の取り組む課題解決活動をより発展させることに繋がると感じました。 発表後の交流の時間では、発表をし合ったグループとは違う方と、自分たちが取り組んでいる活動などについて話し合いました。少しリラックスした雰囲気で、学校、年齢問わず交流することができました。発表の時間とは違う角度で感化されました。 このような機会を頂けて感謝しています。今回の経験、頂いたアドバイスを今後の活動に活かし、より積極的に取り組んでいきます。
- まず、自分たちの研究発表についてですが、他校の先生方などたくさんの方々にアドバイスを頂き、更に質の良い研究していきたいと思いました。商品を作る際の実験に関しては、さらに細かいデータを取り、より確実性のあるものにしていきたいと感じました。大会を通して特に印象に残っている発表は、ディスレクシアという一種の脳機能障害を題材としたものでした。研究当事者がその症状をかかえており、その障害によって日々どのような行動が困難であるのかなどわかりやすく解説してくれました。障害というものは、目に映り判断しやすいものから判断しにくいものまで幅広く存在しています。今回題材となっているディスレクシアは、私たち班員、話を聞いてほぼ初めて詳しく理解したという者が多かったため、一般的には連想されにくいものだと感じました。そのような症状を周りに発信するため、まずは自分のことについて調べ、より深めていく。そういった繰り返し繰り返しの研究動作を細かく行っていることが素晴らしいと思いました。当事者の、主体的に取り組む態度に感銘を受け、私たちのこれからの探究活動に生かしていきたい姿勢を学びました。非常に大きな経験となりました。今大会に出場できたことを、とても嬉しく思い、また沢山の知識を得られたことに感謝しています。これからの探究活動を積極的に行っていきたいと改めて思うきっかけとなりました。
- 今回の探究フェスタでは、他の学校の探究を聞いたり質問しあったりすることで、自分たちの探究を見直すことができました。私たちが聞いた発表は、私たちのテーマと同じ食品関連のものが多かったので、参考になる部分も多くありました。また、質疑や講評を通して、私たちがプラスの面しか見ていないということや、根拠が少ないということなども分かったので、それらをこれからの探究にいかしていきたいです。
- 発表をしているとき、緊張して原稿ばかりを見てしまったことを反省しています。また、1つのスライドに複数の情報を載せているため、手でどこの話をしているかを指すように意識すべきだと思いました。また、いただいた質問は、自分たちだと思いつかなかったものもあったので、他の地域の人との意見交換はとても重要だなと感じました。 他のグループの発表を聞いているときは、私達と同じ食品について発表しているチームが多く、様々なグラフを示して説得力を増している点がとても良いなと思いました。また、郷土料理チームの発表で紹介していたインスタグラムを用いた普及活動は、私が「総合的な探究の時間」の探究チームで行っている子ども食堂の研究においても、活かせる点だと感じました。 交流会では、1日の発表を通しての意見交換を行いました。発表の教室よりも、沢山の学校の人と話すことができました。また、それぞれ研究内容が様々だったのですが、ほとんどのチームがフィールドワークに行っていたり、実際に実験をしていたりと、考えるだけでなく実行することが大切だと感じました。 今日1日を通して、今まで他校の人との意見交換の場がほとんど無かったので、自分達には無い視点でアドバイスをもらうことができて良かったです。また、食品についての研究をしているチームが多く、自分達の活動とリンクする部分も多かったので、とても貴重な時間でした。私達は今まで、実際に行うためにかかる費用のことや、発表に説得力を持たせるためのデータについて詳しく調べてこなかったので、そのあたりも調べて、より具体的な良い発表にしたいと感じました。
- 今回の探究フェスタでは、他のチームの発表を聞いた上で、自分達の発表の改善点が明確になりました。とくに自分が思ったのはスライドで、他のチームはデータや具体的な数字を出して根拠をはっきりさせた一方、自分達は 「○○を聞きました」という表現になってしまい、具体的なデータは出せておらず、せっかく集めた資料を有効活用できませんでした。その他にも発表中の視線が台本に行ってしまったことや質疑応答を上手く出来なかったことなど、ダメだった部分を反省してこれからの活動に繋げていきたいです。

